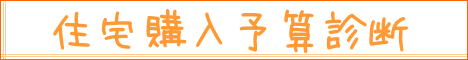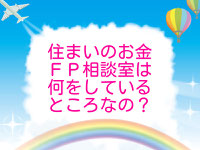共有名義で購入する場合の注意点とは?|住まいのお金FP相談室

マイホームを購入する際、夫婦やご両親など、複数の方がお金を出すケースは少なくありません。
「夫婦で一緒に住宅ローンを返すから共有名義にしたい」
「親が資金の一部を援助してくれたから、登記にも名前を入れたい」
こうした考えはごく自然なことです。
しかし、実は共有名義での住宅購入には、「贈与税」という思わぬ落とし穴が潜んでいます。
登記の割合を間違えると、税務署から「贈与があった」と見なされ、多額の贈与税が課されることもあります。
この記事では、共有名義の基本から、正しい登記割合の考え方、そして注意すべき税金のポイントを、分かりやすく解説します。
1.共有名義とは? そもそもの基本を理解しよう
「共有名義」とは、住宅や土地などの不動産を、複数の人が共同で所有することをいいます。
登記簿上で、たとえば「夫2分の1、妻2分の1」といった形で持分割合を記載します。
共有名義にする主な理由は次のとおりです。
・夫婦でお金を出し合って購入した
・親子でお金を出して購入した
・相続対策として名義を分けておきたい
一見すると合理的な仕組みのように思えますが、実際にお金を出した割合と、登記の持分割合が一致していないと、贈与とみなされてしまう点に注意が必要です。
2.登記割合と出資割合がズレると、なぜ贈与になるのか?
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
・住宅価格:5,000万円
・子ども(購入者本人)が4,000万円を出す
・両親が1,000万円を援助する
この場合、資金の出し方に応じて考えられるケースは3つあります。
① 1,000万円を「もらう」場合
両親から1,000万円をもらって子どもが家を買えば、これは明らかに「贈与」です。
ただし、住宅取得資金の贈与には非課税枠が設けられており、一定の条件を満たせば税金がかからない場合もあります。
しかし、非課税枠を超えると贈与税の対象になります。
※非課税枠は年度ごとに変わるため、最新の税制を確認する必要があります。
② 1,000万円を「借りる」場合
もし両親から「借りた」という形にするなら、借用書を作成し、返済計画を明確にしておく必要があります。
利息を支払わない場合、税務署から「実質的に贈与だ」と判断される可能性もあるため注意が必要です。
③ 両親との「共有名義」にする場合
最も自然な方法がこれです。
両親が1,000万円を負担したなら、その資金の出資割合である5分の1(1,000万円 ÷ 5,000万円)の持分で登記します。
こうすれば、両親は「自分のお金で自分の資産を取得した」ことになるため、贈与にはあたりません。
3.具体例で考える共有名義の登記割合
例1:親子でお金を出し合って購入する場合
・住宅価格:5,000万円
・子ども(購入者本人):4,000万円
・親:1,000万円
この場合、子どもが持分5分の4、親が持分5分の1として登記すれば、税金上も問題ありません。
例2:夫婦で住宅ローンを組む場合
・住宅価格:5,000万円
・夫:住宅ローン4,000万円
・妻:住宅ローン1,000万円
この場合、夫の負担割合は80%、妻は20%です。
登記もそれに合わせて、不動産の持分を「夫:5分の4、妻:5分の1」とするのが基本です。
もし半分ずつ(2分の1ずつ)などで登記すると、妻が実際に拠出した資金よりも多くの資産を得たことになり、夫から妻への贈与と判断される可能性があります。
4.意外と多い「贈与と見なされる」ケース
共有名義に関するトラブルで多いのが、“気持ちで名義を入れてしまう”ケースです。
(1)せっかくだから夫婦で半分ずつ
実際には夫の収入だけでローンを組み、妻は一切お金を出していないにもかかわらず、「夫婦だから半分ずつにしたい」とするケース。この場合、夫→妻への贈与とみなされる可能性が非常に高いです。
(2)親の資金援助を受けたが、全額子ども名義で登記した
よくあるのが「親が資金援助してくれたけれど、登記は100%子どものみ」というケース。
これは、金額が大きければ贈与税の対象となる可能性が高まります。
住宅取得資金の贈与の非課税制度を使わない場合には、贈与税の対象になる可能性があるため注意しましょう。
(3)夫婦共有の預金から出した場合
共働き夫婦の場合、「夫婦共有の口座から支払った」というケースがあります。
しかし、その口座にどちらがどれだけお金を入れていたかで、実質的な出資割合が異なる場合があります。
税務署は資金の出どころを重視するため、記録を残しておくことが重要です。
5.共有名義のメリットとデメリット
共有名義で不動産を購入することは、必ずしもメリットばかりではなく、デメリットも存在します。
◎メリット
・出資割合に応じて公平に所有できる
・親子や夫婦で資産を共有できる
・住宅ローン控除をそれぞれが受けられる(一定条件あり)
△デメリット
・登記割合を間違えると贈与税のリスクが生じる
・売却や相続の際にトラブルになりやすい
・住宅ローンの手続きが複雑になる場合がある
とくに親子で共有の場合、将来的に相続が発生したときに手続きが複雑化することもあります。
親の持分を子どもが相続する形になりますが、他の兄弟姉妹がいる場合には、遺産分割の対象になることもあるため注意が必要です。
6.共有名義にするときの3つの注意点
① 資金の出どころを明確にする
「誰がいくら負担したのか?」をきちんと記録しておきましょう。通帳の振込記録や領収書など、客観的な証拠を残すことが大切です。
② 登記割合は出資割合と一致させる
不動産登記の持分割合は、「出したお金の割合」と一致している必要があります。曖昧にせず、しっかり計算して登記を依頼しましょう。
③ 契約前に専門家に相談する
税金や登記の問題は非常に複雑で、後から修正ができない場合もあります。購入前にFP・税理士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
7.共有名義を検討するときにFPができるサポート
ファイナンシャルプランナー(FP)は、単にお金の計算をするだけでなく、次のようなサポートが可能です。
・資金計画の作成(誰がいくら負担するか)
・贈与税や住宅取得資金の非課税の制度活用のアドバイス
・将来の相続を見据えた所有割合の提案
・住宅ローン控除の最適化
「共有名義にするか迷っている」
「どんな割合で登記すればいいか分からない」
そんな時は、購入前に相談することが最も大切です。契約後や登記後では、修正が難しくなるケースが多いからです。
8.まとめ:登記割合=出資割合が原則!
共有名義で住宅を購入する場合、一番大切なのは次の一言に尽きます。
「登記割合=実際に出したお金の割合」
これを守れば、基本的に贈与税の問題は生じません。
逆に、この原則を守らないと、思わぬ税負担や将来、相続トラブルに発展する可能性があります。
・出資割合と登記割合を一致させる
・証拠となる振込記録を残す
・専門家に早めに相談する
この3点を意識しておけば、安心してマイホームの夢を実現できます。
「夫婦で力を合わせてマイホームを買いたい」
そんな気持ちはとても素晴らしいものです。
ただし、登記や税金のルールを正しく理解していないと、思わぬトラブルを生むこともあります。
共有名義は、家族の協力を形にできる素晴らしい方法です。
迷ったときは、FP・税理士・司法書士などの専門家にぜひご相談ください。

「住まいのお金FP相談室」では、松戸市・柏市・流山市・つくば市を中心に、マイホーム購入前の お金の不安や迷いを、中立な立場でサポートしています。
住宅会社や不動産会社ではない、第三者の立場のファイナンシャルプランナーだからこそ、あなたとご家族にとって最適な選択を一緒に考え、アドバイスする事が可能です。

いくらまでならマイホームにお金を使っても「教育資金」や「老後資金」を問題なく準備ができるかご存知ですか?
あなたが買っても大丈夫な「マイホーム購入予算」を住宅相談専門のファイナンシャルプランナーが診断します。

メニュー
家づくりナビ/マイホーム/住宅設備/収納/インテリア
モデルハウスの実例から学ぶ
✦失敗を防ぐポイント
✦真似したくなるデザイン・アイデア
✦知らないと損する情報・裏ワザ
インスタグラムで配信中!
住宅相談以外のFPメニュー
住宅購入後の
家計の見直し相談
住まいのお金FP相談室

松戸市のファイナンシャルプランナー
住まいのお金FP相談室 松戸店
JR常磐線・千代田線・新京成線 松戸駅 西口徒歩3分
柏市のファイナンシャルプランナー
住まいのお金FP相談室 柏店
つくばエクスプレス
柏の葉キャンパス駅徒歩1分
つくば市のファイナンシャルプランナー
住まいのお金FP相談室 つくば店
つくばエクスプレス
つくば駅徒歩15分
【オンラインFP相談室】
小さなお子様がいるなど、外出が大変なお客様は、ご自宅にいながらオンラインにてご相談が可能です。
担当ファイナンシャルプランナー

【CFP 真崎 喜雄】
幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。
メディア掲載実績
全国のFPが会員登録している日本FP協会様より、実務家FPとして取材を受けました。


「シンヴィング」様より住宅購入相談FPとして取材を受けました。(クリックで拡大します)
工務店さん向けに「工務店が知っておくべき資金計画」の研修講師を行いました。


ニューファミリー新聞社様にて、著書「生命保険見直し成功マニュアル」が紹介されました。